
スティーブン・クラッシェン(Stephen Krashen)はアメリカの言語学者で、第二言語習得における重要な理論・モニターモデルを提唱しました。
このモニターモデルは「5つの仮説」を総称したものですが、日本人が英語を習得するなど第二言語の学習において非常に役立つ情報とです。
など、気になるポイントを一通り解説した上で、英会話習得のコツを確認しておきましょう!
ページコンテンツ
はじめに、クラッシェンのモニターモデルに関して概要を説明します。言語学や第二言語習得の領域で大きな影響を与えたクラッシェンについて、英語学習をしたい方はぜひ知っておくといいでしょう。

スティーブン・クラッシェン(Stephen Krashen)はアメリカの言語学者で、簡単なプロフィールは以下の通りです。
クラッシェンは言語学者・教育学者だけでなく政治活動家としても知られていますが、世界的には第二言語習得の領域で特に知名度が高いですね。
以下でも紹介するモニターモデル(5つの仮説)は、語学教育において大きな影響を与えました。ただ、完璧な理論とも言えず一部の識者・学者より批判の声もありますが、それでも第二言語を学ぶ人にとって参考になるノウハウが詰まっています。
クラッシェンは2022年現在も現役で、言語習得に関する解説動画をYouTubeから視聴できます。彼自身の肉声など気になる方は、以下の動画もぜひご覧ください。
モニターモデルの詳細でも確認できますが、英語を話せること=言語としての知識や経験だけでなく、やる気や不安などマインドによる要因もあり、総合的な語学力上達のポイントが分かるようになるでしょう。
クラッシェンのモニターモデルは、以下5つの仮説をまとめた概念のことです。

どれも重要なことで、英語・英会話の独学で役立つ知識となるでしょう。
これまで英語の独学に失敗した人や、英会話スクールに通ったけど効果が出なかったなど、挫折経験のある方でも正しい英語学習・語学への向き合い方を知ることで上達のコツを体感できます。
モニターモデルの各詳細を解説する前に、どうしてクラッシェンの理論を理解する必要があるのか?といったポイントを説明します。
言語学的な専門領域になり、難しそうだからなるべく触れないでおきたい…と思う方もいるかもしれませんが、特に初心者だからこそモニターモデルを知っておくメリットが大きいです。

英語を話せない人の大半が、「何が原因で英会話ができないのか」原因が分からないままとりあえず独学を続けているケースがあるでしょう。
基本的な英語の知識があっても、会話・コミュニケーションとしての必要なスキルを知らないと原因と対策が理解できないでしょう。そこで、言語学的な見識から確認することで英語を話すために必要なポイントが見えてきます。

学校での英語学習のほか、TOEIC対策をしても英語を話せるようになれない人は多くいます。
Aloha English英会話でもそのようなお悩みに関する問い合わせ・相談があり、TOEICで900点以上を取れていても英会話が苦手…という方は多くいます。
学校での英語やTOEICでは、参考書などで明確な対策はできます。ただ、英会話に対して必要な学習を知らないと、インプット学習はできてもアウトプットは苦手なままでしょう。

上記の理由と関連して、クラッシェンのモニターモデルによって英語の勉強・独学を正しく修正して、効率を上げられるメリットもあります。
特に初心者にありがちな失敗で、効果的でない学習を続けてしまって時間の無駄に終わる・諦めてしまいます。
といった学習をしている初心者は要注意で、あまり上達が見込めない状況にあります。
中には我流の勉強をしたり、英語が話せるようになった人のブログ記事を参考にする初心者もいますが、大事なのは学習における成功体験の再現性です。
語学習得では個人差もある中で、言語学者による普遍的な理論・学習法は信頼性が高いです。そのため、個人の感覚や判断で学習計画を立てるよりは、まずは専門家による学習モデルを活用した方が良いでしょう。
クラッシェンのモニターモデルを具体的に解説しますが、まずは1つ目の仮説・理論である「習得学習仮説」を見ていきます。
習得学習仮説では、習得(acquisition)と学習(learning)について別々の考えを示します。

習得は赤ちゃんが母国語を覚えるようなプロセスで、自然と無意識下で行われるものです。学ぶというより、体験する・感じるといった具合で言語を覚えます。
クラッシェンは、学習は習得と異なる部類で定義付けています。学習では能動的に勉強するように、意識的に行われるものです。
学習もある程度の重要性があるものの、クラッシェンは第二言語習得において、母国語と同じように無意識で(習得を率先して)学ぶことがより重要だと提言しています。
大人になってしまったら母国語習得のように、子供と同じような覚え方は難しいのではと思うかもしれませんが、大人も子供と同様な覚え方は可能だとされています。
「自然に」「無意識で」言語を覚えることの定義について不明確といった批判もありますが、分かりやすく表現すればネイティブと同じような感覚で言語を扱えば習得できるといった感じです。

例えば友達との会話で「昨日、仕事帰りに有名やパン屋へ行ったんだけど、正直そこまで美味しくなかった」と言われた際に、
など、そこまで深く考えることはなく「残念だったねー」みたいな返答を反射的にするかと思います。
同じような感じで、英会話においても聞いた英語に対して文法の深掘りや日本語訳などをせず、英語のまま認識することで、習得的な環境で言語を学ぶことができるでしょう。

クラッシェンの見解では習得と学習は明確な区別があるとされていますが、学習によって得た知識が習得に影響する反論もあります。
英語の習得において、基本的な文法などインプットでの学習がなければ話すことができません。これはインプット仮説でも説明していますが、意識的な基礎固めをしないと話す知識が得られないでしょう。
そのため、無意識的な習得と意識的な学習については以下の要点が挙げられます。ここでは、よりレベルの高い第二言語を習得するには、無意識での言語利用が利用といった程度の認識で問題ないでしょう。
続いて、モニターモデルの一つである自然習得順序仮説を説明します。クラッシェンは、言語の習得において決まった順序・順番があると提唱しました。

具体的には、子供の頃に英語を習得する場合に自然と覚えやすい順序で文法を習得するといった考え方が、自然習得順序仮説に該当します。
動詞を例に出すと、動詞の原型や進行形(-ing)や複数形(-s)のほか受動態などありますが、覚えやすい順序があります。
動詞原型や進行形、複数形は比較的変化のルールが分かりやすく、早い時期に覚えるものとされています。「speak/speaking」や「cat/cats」などがその例だと言えるでしょう。
対して、受動態や不規則動詞など一定のルールから外れるような語形変化は、比較的習得が遅くなります。「go/went」や「arise/arose」などが該当するでしょう。

ただ、自然習得順序仮説に関しても以下の通り反論があります。
といった特徴があるため明確なシラバス(授業計画)がないというのが実情ですが、語学初心者にとって、学びやすい順番から段階的に覚えるやり方自体は正しい方針です。
クラッシェンの提唱内容とは別で、Aloha English英会話でも効率的な学習を実現できる文法の覚え方・順番について提案しています。初心者は文型や構文から覚えることが大事など、英会話講師の視点で学習のステップをまとめました。
詳しくは、英語の文法を効率よく学ぶための順番・勉強法でご紹介しています。実践的な独学のノウハウもぜひ活用してみてください。
モニターモデルの3つ目の仮説・モニター仮説では、最初に紹介した習得学習仮説と関連があるものです。
先ほども少し説明しました習得と学習について、基本的には言語の運用において習得(無意識での活用)のみが有効だとクラッシェンは示しています。
ですが、学習が無意味というわけではなく習得によって表現された発話・アウトプットの修正や改善において学習(意識的に得た知識)が役立ちます。
習得と学習の関係を説明すると、以下イラストのような感じとなります。実践的なコミュニケーションでは習得された言語が働きますが、その言語の正誤を学習で得た知識によって確認・修正がされます。

習得学習仮説では、言語のレベルをあげるには習得が必須だと説明しましたが、モニター仮説で掘り下げると習得した言語のクオリティを高める上では学習の働きも欠かせません。

ただ、学習による知識からの言語修正が過剰でも良くなく、文法や単語などの表現の正確性にこだわってしまうと自然な会話が難しくなるでしょう。
日本人の英語習得においてよくある課題で、文法など完璧な英語を求めようとすると本来の機能である他者との会話がぎこちなくなってしまう恐れもあります。
モニター仮説から考察できることの大事なポイントで、英会話では間違いに気付くことで上達します。自分のアウトプットが正しいかどうか判断した上で、間違っていたら修正をしてどんどん覚えていきます。
変な英語を話してしまうことでの恥ずかしさや躊躇いは、語学力アップの妨げになるでしょう。英語での会話で不安のある方は、英語コミュニケーションで重要なマインドセットもご参考ください。
続いて、クラッシェンの第二言語習得理論で特に知られている「インプット仮説」も見ていきます。インプット仮説もモニターモデルの一つで、クラッシェン自身も最も重要な仮説だと提言しています。

言語習得では、文法や英単語など基本的な知識を得るインプット学習が最重要だとされます。
インプットの重要性について、第二言語習得理論の解説ページでも取り上げていますが、インプット仮説だけの見解では、第二言語習得においてインプットだけが重要でアウトプットの必要性には触れていません。
インプット仮説で提唱されているインプット(言語の知識)は、「理解可能な」条件があり、理想的な習得レベルの定義がされています。

インプット仮説によると、勉強をする自分自身の語学レベルを「i」と示した上で、少し高いレベルである「i+1」の学習により自然と習得できます。
自分の語学力とは同じレベル「i」や、より高いレベル「i+2」でもない少し上のステップを目指すことが理想ですね。
ただ、「i+1」の基準とは何なのか? という疑問を感じる方もいるでしょう。以下でもインプット仮説の批判で、レベル基準が曖昧といった課題も説明しています。
ただ実践的な例があり、基本的にはCEFR(セファール)の基準に従うことで学習レベルの設定が明らかになります。
といった流れで、まずは自分の英語レベルを知るところからスタートします。CEFRでの語学習得レベルはA1〜C2までの6段階があり、自分がA2レベルだったら一つ上のB1向けの学習をすることになります。

また、B1など一つの学習レベルの中でもインプット型の学習ができているかどうかなど4つのステップ・習熟度で分類されます。
以下図のように、B1の学習が始めてという場合には①知る+②理解の内容からはじめ、慣れてきたらアウトプット型の対策をします。

「i+1」のインプット学習に適さない例として、CEFR:A2レベルの人が「英語の聞き流し学習」を行うというケースがあります。
まだ英語のリスニングスキルが不足しているA2の人がネイティブ英語や海外の映画、ニュースなどを聞き流ししたとしても学習効果は得られないでしょう。聞き流しは学んだことを復習してよりリスニングの精度を上げることが期待できますので、上級者向けの対策となります。
「i+1」の考え方に則ると、B2またはC1の人が「聞き流し学習」をすることでi+1の法則が成り立ち、効果を発揮できます。
「i+1」を上手く実践している学習例について、以下でまとめてみました。英語スキルの4技能(話す・聞く・読む・書く)それぞれの独学について、どれほどのレベルが適切なのか参考までにご確認ください。
リーディングもリスニングと同じように、初級者用の教材を使っていた人が中級者向けの教材を使うといったイメージになりますね。
「なんとなく、シャドーイングが効果出るからやってみる」とか「今SNSでこの教材が人気だから試してみる」など興味本位での対策をする方も多いですが、クラッシェンの理論を基準に考えると、確実なステップアップを望めるでしょう。

このインプット仮説について、以下のような批判もあります。
このインプット仮説だけではアウトプットの必要性を否定されているため、他の学者からはアウトプットの重要性も説かれています。
実際、英語習得においてインプットだけでは話せるようにはなれず、コミュニケーション面でのスキルを身に付けるアウトプットの対策をして初めて、英会話ができるようになります。
インプットとアウトプットのバランスや重要性について、形式文法と機能文法の関係にも通じるところがありますので、気になる方は関連ページもぜひお読みください。
最後のモニターモデルである「情意フィルター仮説」は、自身の感情や気持ちによって言語の習得効率が変わってくることを示しています。

情意フィルターの「情意」は「感情」や「意志」などを意味するように、言語を使ったコミュニケーション・学習では個人の感情などに左右されます。
仮に英語の基礎スキルが高い人でも、「自分の英語力に自信がない」とか「英語習得の目的がない」など消極的・ネガティブな考えにとらわれていると、習得能力が低下するでしょう。
クラッシェンは情意による影響も大事だと言っており、言語の習得において妨げになるマインドはなるべく無くすようにしましょう。

逆を言えば、英語力は低い人でも「絶対に今年までには英会話ができるようになる」とか「英語学習がとても楽しくずっと続けていられる」など、自信やモチベーションの高さがあればメキメキ上達します。
これから英語学習に取り組む方はぜひ、前向きなマインドや明確な目標を立てて勉強してみるといいですね。参考記事で、英会話の学習ゴールや目標の設定方法もお読みいただけますと幸いです。
モニターモデル(5つの仮説)を一通りご紹介しましたが、クラッシェンはモニターモデル以外にも言語習得で大事な理論を提唱しました。
その一つがナチュラル・アプローチで、クラッシェンと応用言語学者のトレイシー・テレルによって生み出されたものです。
ナチュラル・アプローチでは自然なコミュニケーション能力の習得を目的として、以下3つの原則に従います。

ポイントとして、実際のコミュニケーションを通して言語を覚えていくやり方で、文法がある程度間違っていても会話が成立していれば許されるような特徴があります。

最終的には完璧な文法・表現で英会話ができると良いですが、少しずつ会話に慣れていき能動的なコミュニケーションが取れるといったナチュラル・アプローチの考え方は実用的です。
日本の英語教育もスピーキングなど4技能の総合的な対策が取られるので、学校の授業でもナチュラル・アプローチに基づいた会話練習も今後行われるでしょう。
また、子供だけでなく大人の英会話学習でも大事なマインドです。文法や表現の正確さを求めるより、まずは会話に慣れていくとアウトプットも上達しやすくなります。特に会話への苦手意識がある方は、自然な発話という点を意識してみるといいでしょう。
クラッシェンのモニターモデルについて「習得」と「学習」や「インプット」と「アウトプット」など、対照的な要素やそれぞれの働きなど、大事なポイントがあったかと思います。
ざっくりまとめると以下の通りで、英会話の習得では幅広い対策が求められます。
学校やTOEICで学ぶ英語は正確さが求められますが、クラッシェンのモニターモデルでは実用的な会話・コミュニケーションスキルに焦点を当てて、上達するポイントを掘り下げました。
これまで英語が苦手で独学で成果が出なかった方も、今一度クラッシェンの理論を意識して取り組んでみると、学習成果を感じやすくなるでしょう。具体的な勉強法をもっと知りたい方は、英語が苦手でも3ヶ月続けるコツや、時間のない社会人でも英語学習を続けられる対策など関連記事からぜひご確認ください。

Aloha English英会話の専門家が
英語学習のお悩みや目標をヒアリングし、
あなたにあった学習法をご提案します。

担当者がじっくり日本語でお話をお伺いします。

英語で話すことが苦手な方はぜひご相談ください。

英語の聞き取りに関するお悩みもご相談できます。

英会話力を上げるための方法についてもご相談できます。
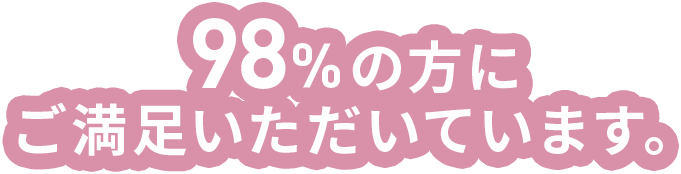
Aloha Englishの無料カウンセリングは
オンラインでのお打ち合わせとなります。
3ステップで簡単にお受けできます。
まずはご予約をお願いします。
お客様の都合に合わせて、カウンセリングの日時をお選びいただけます。
予約後、担当者から送られるリンクで
Skypeに接続します。
Aloha Englishの日本人講師に、あなたの目標や学習スタイルに合わせた相談ができます。
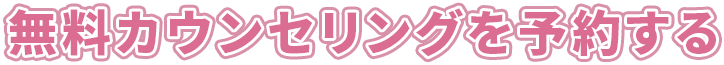
60秒で完了する簡単なステップで、
無料カウンセリングの予約が可能です。
コメントを投稿するにはログインしてください。